神楽坂コラム
#1 毘沙門天善國寺 嶋田堯嗣住職に聞く


神楽坂通りのほぼ真中に鎮座して、数百年のまちの発展を見てきた毘沙門天善國寺。その境内に特設ステージを設け「講釈場」に見立てるなど毘沙門天善國寺は、「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」の重要な場所としての役割を果たしてきました。通りに面した劇場空間は、そのまま江戸へタイムスリップしそうです。第1回目から、メイン会場としての使用に理解と協力をしてくれた住職の嶋田堯嗣さんにお話をうかがいました。
ーこのイベントに関わったきっかけはどんないきさつですか?
一番最初は、NPO法人粋なまちづくり倶楽部の日置さんがうちにいらして「神楽坂のまち中でイベントをやりたいので場所をお借りしたい」というお話でした。最初は「なんでうちなのか?」わからない部分もあったのですが。お話をうかがっているうちに納得をしました。うちはお寺ですから、お経はいつも読んでいますよ。そのお経の中に仏様の世界を描写しているところがあって、そこには美しい花園、美しい森、大きな建物などいろんな世界が出てきます。天上界には宝の花の咲く草木が咲き誇り、音楽とか舞踊とかが演奏されていて、天からは曼荼羅という花びらが舞い落ちて、仏様の上に降り注いでいる。天の鼓があちこちから鳴り響き……。といった描写がお経の中にちゃんとあるのです。ですから、音楽とか舞踊とかをお寺でやるのはもともとご縁があると思っています。ですから会場になることに賛同しました。
ー神楽坂のまちの中心としてたくさんのイベントが実施されていますが?
神楽坂の夏祭りでも、以前から境内にやぐらを組んで、さまざまな歌や音楽で祭りを盛り上げる演出はありました。これらは地元の商店街が主催しているもので古典芸能の時もあり、歌謡曲の時もあり、和太鼓の演奏の時もありましたね。でもこのイベントは、祭りを盛り上げるためのものではなく、古典芸能そのものをまち中で楽しんでもらうというものだから、そこが新しいですね。毘沙門天善國寺は、まちとのつながりを大切にしたい思いから、こうしたイベントはできる限り協力していきたいと思っています。とはいっても、ご存知のようにうちは土地の面積が狭いので、大々的なことはできません。逆にいい点は、表通りに面しているので、何かやっていると通行している人の目にすぐ入ってきます。その点は恵まれています。
ー実際に会場となってみて、どんな思いをされていますか?
もう6年目になりますが、実際にやっていくうちにお互いのやり方がわかってきますので、こちらからの注文は遠慮なくはっきりとお伝えして、修正できる点は修正してもらっていますから何も心配はしていないのですが、毎年開催される11月はお寺の七五三の時期と重なるので、音を小さくしたり、音をいったん止めてもらうなどしたことはあったと思います。一つ注文させてもらえば、開催時期はお寺の行事の多い秋ではなく、春の5月頃にお願いしたいですね。
ー歴史と伝統のあるお寺として、まちのイベントとどのように関わっていかれますか?
毘沙門天善國寺は戦災で全焼してしまいましたが、毘沙門像など大切なものは全部千葉勝浦に疎開していたので無事でした。石造の狛虎像も火災の熱で一部こわれましたが、なんとか残りました。そして昭和26年に木造の小さな本堂を建てたのです。しかし、参拝にいらした方から「これがあの天下の毘沙門天か」といわれるぐらい質素だった時があったのです。それを昭和46年に建て替える時、さらに平成5年に山門などをつくる時も神楽坂の商店街をはじめ地元の方々に助けてもらい、やっとこの寺も大きくなれたのです。まちの発展と一緒に栄えてきました。「寺がよくなればまちもよくなる」という地元の方々に支えられて来た歴史があるのです。そのありがたい思いに応えていきたいと考えています。さまざまな人が参集する場所として、伝統芸能の会場として、お寺とまちが一体となって発展していくことが理想だと思います。
#2 神楽坂芸妓組合 眞由美姐さんに聞く


毎年入場チケットがあっという間に完売してしまうほど人気の「覗いてみようお座敷遊び」。このコーナーに出演いただいているのが東京神楽坂組合(※1)の芸者さんたち。その芸妓組合組合長の眞由美姐さんに花柳界とまちのイベントへの思いを語っていただきました。
ー最初にこのイベントに参加された時の印象はいかがですか?
まちの皆さんに私たちの芸事をお見せするのは、春の「神楽坂をどり」や秋の若手の会「花みずか会」など、さまざまな機会をいただいていますので、それほど心配はなかったのですが、芸妓組合長となって最初の年は始まりのご挨拶に戸惑いました。外国のお客さんのために同時通訳の方が入っていましたので、話を短く区切りながら英語訳を待って、次の言葉を発するということに慣れていなかったですね。でも、国際化というのでしょうか、外国の方に日本文化に興味をもっていただけるのはとてもよいことだと思います。
ー見番の中で行われるのですね?
見番は私たちのお稽古場として日々利用しているところですが、その見番の中に一般の方をお招きしてお見せできるのも特色の一つになっています。おけいこ場ですから、劇場のように広くはありませんが、逆に近いだけに親しみが感じられる空間だと思います。
ー今年の演目を教えていただけますか?
今年の出し物は、端唄「紅葉の橋」、小唄「辰巳よいとこ」、「神楽坂さわぎ」です。「神楽坂さわぎ」は、牛込箪笥区民ホールで「神楽坂をどり」の時のフィナーレで踊る「さわぎ」ではなく、いつもご指導いただいている花柳輔太朗先生と清元志津子太夫先生のオリジナル作品です。出演するのは地方が4名、立方が3名。地方は、三味線が夏栄姐さんと櫻子さん、鳴物が由みゑさんで、私が唄。地方のほうは替わりませんが、立方は毎年替わりまして今年は、桃子さん、小夏さん、?よ乃さんの3人が出演しますので、どうぞお楽しみに。
ー毎年たいへん盛り上がるとお聞きしていますが?
芸事の後には、お客さんも一緒になって楽しんでいただけるお座敷でのゲーム、これが毎年大好評で、かならず盛り上がっています。「虎虎」「金毘羅船船」、それに最近の人気「お猪口くるくる」です。これは最近始めたのですが、グループごとに勝ち上がってきた勝者同士で決勝戦をします。皆さん本当に熱くなって、大盛り上がりのゲームなんですよ。
ー花柳界とまちの文化についてどのようなことを期待されていますか?
神楽坂の歴史を振り返ってみますと、やはり商店街と花柳界が一緒になって一つのイベントで協力し合っていく、そういう傾向が生まれてきたことはここ10年、15年ぐらいのことではないかと思います。まちが発展していくことに花柳界が協力し、まちの人たちも日本文化や伝統芸能の良さを再発見していただける、これはうれしいことですね。「おもてなし」という言葉が世界の共通語のように使われる時代に、私たちの日頃お稽古してきた成果がお役に立てて、神楽坂のまちの魅力の一つにつながっていく、これは協力し甲斐のある内容で、感謝したい気持ちです。
※1 神楽坂の料亭組合と芸妓組合が一緒になった団体が「東京神楽坂組合」
#3 神楽坂商店街振興組合 横倉泰信理事長に聞く
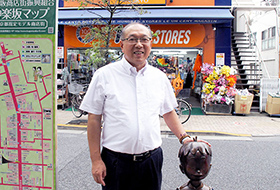

「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」の舞台である神楽坂のまち。その神楽坂6丁目をまとめているのが、神楽坂商店街振興組合の横倉泰信理事長です。神楽坂のまちの良さやイベントへの関わりなど、熱い思いを伺いました。
ー横倉理事長ご自身や所属する団体と、神楽坂の関わりをお聞かせください。
神楽坂商店街振興組合は、商業だけでなく環境を整えたり設備を考えたり安全・安心という、地域全般と関わり合いながら安定を図っている商店街であります。
ー当イベントとはどのように関わられていらっしゃいますか?
神楽坂という名前の由来はお神楽から来ていて、神社のお神楽殿から音色が聞こえてくるという、もともとの下地に神社や古典芸能があります。このお祭りで、皆さんが伝承しているものを、まちの中に広げていけることがステイタスだと感じています。そもそもそうしたことが可能なのも、伝統芸能とともにあるまちだからです。江戸時代からの積み重ねで、継続している伝統や文化が、自然と根付いているからですよね。
ー6丁目の商店街のご協力は、路上ライブのためにパークリュクス神楽坂前ポケットパークを借用、電源や駐車場手配などがありますが、実際にご協力くださってどのように感じましたか?
伝統や文化という土台を匠の方にやっていただいているので、自分たちは少しでもそのサポートが出来れば良いかなと。携わる匠の方も日々、芸の研鑽を積んでご苦労なされていると思いますが、それを支えるさまざまなサポートがあって初めて発表出来ると考えています。動線として赤城神社があって、スタンプラリーのルートにもしていただいて、みなさんがまちを巡る。まち全体が会場になっているから、通るだけでそこが舞台になり、新しい物語が生まれてくると思うんです。人の流れはそれぞれの神社仏閣が結びとなっていて、自然と物語の背景があるんですよ。我々が言うのはおこがましいけれども、それが神楽坂のブランドではないかと思うんです。しっかりと伝統と文化という根が張っているので、ブランドとしてあらためて耕しても本物を楽しめる。今から開拓するのとは違うんです。それが出来るのも、町の人の絆と一本筋の通った誇りがあるからこそです。
粋な黒塀ってのはガードなんですよね。中に入ると素晴らしく楽しいところなんですが、それは外には伝わっていかない。そこが良さでもあったんですけれども、この祭りをきっかけに少し扉が開いたんですよ。でも全部晒すのではなく、隠しながら奥深さを見せていくという。神楽坂って親しみやすい人懐っこさもあるけれども、ちゃんとさらっと引くところは引くという気持ち良さがある。お節介焼きたいんだけれども、最後のところで控えちゃう、それが粋なんですよね。ちゃんと人との距離を測りながら、見守っている。そういう部分をあらためて感じました。
ー忙しい時代だからこそ、皆さんここに来ると、癒されると言ってくださいますよね。
今はどんどんとテクノロジーが進んでいるけれども、こういうゆったりとした古典的な音をまちの中で聞けて、心が癒されるのが神楽坂の良さで、またそんな風にお客様に満足してもらえるのが、我々のモチベーションに繋がっていると思います。最近、商店街も女性陣が頑張ってくれて、各お店もいい感じに整ってきていて。それらが上手く循環して、街に活気をもたらしていますしね。今回の祭りも含めて、四季折々の行事が整ってきているというのかな。新しいものを加えて、街が良い方向に進んでいくように、我々ももっと協力して盛り上げていきたいと思っております。
ーこのイベントに参加したとき、どのように感じられましたか?
とにかく素晴らしい、それが第一印象ですよね。演者の方たちの尺八やお筝などがね、「あー…、ふぅ…」って、人間の呼吸で演奏しているものだからでしょう。日本の楽器の良さはそこなんでしょうね。人の呼吸は古典の時代からずっと一緒ですから、そういう風に感じられる場所があると人は落ち着くし、そんな空間を提供出来るのが素晴らしいなと。
#4 あずさ監査法人CSR推進室 山中知行室長と岩淵温子さんに聞く


毎年、スタンプラリーの場所をお貸しくださったり、ボランティアとしても参加してくださる「あずさ監査法人」。今回はマーケティング&コミュニケーション部CSR推進室の山中知行室長、同社の岩淵温子さん、主催のNPO法人粋なまちづくり倶楽部の日置圭子さんが対談いたしました。
ーあずさ監査法人、また山中室長ご自身と、神楽坂の関わりをお聞かせください。
山中 このイベントや神楽坂との関わりが出来たきっかけは、あずさ監査法人の前身、朝日監査法人が神楽坂に社屋を1995年11月に移転したところから始まります。当時は朝日監査法人という名称でしたが、竣工するビルの高さをめぐって、地元の方々と話し合い協力をいただきました。地元の方々のご協力なしには社屋は出来なかったと、理事長から聞いておりまして。そのような経緯から、自然と神楽坂に関わるようになり、あずさ監査法人として、98年から「神楽坂まつり 阿波踊り」(※1)に参加を始めました。
ーそうして10年が過ぎた頃、日置さんが「神楽坂伝統芸能」(※2)を企画されたんですよね。
日置 そうなんです。当時、人間国宝の方も数多く住まわれている神楽坂の伝統芸能を地元主催のイベントとして形にしたいと、奮闘しておりまして。そのイベントで地元の企業にご協力をいただきたくて商店会に相談した時に、「いつもあずさ監査法人さんに、阿波踊りなどの地元のお祭りで積極的にご協力いただいてますよ」と紹介されて、あずさ監査法人さんにご協力のお願いに上がったんです。
山中 ちょうどその頃ですね、あずさ監査法人にCSR推進室ができたんです。私たちも本業をはじめ、環境や社会などのいろいろな活動を始め出した時に、日置さんがいらっしゃって、熱っぽくいろいろ語ってくれまして。
日置 本当に若気の至りで(笑)
山中 その情熱に打たれて、2009年からボランティアとしての人材を提供させていただいております。私も最初の時にスタンプラリーや歴史ガイド役で…いやガイドと言っても、後ろに付いて行く程度で、実際に説明される方はまちに詳しい方が話しているんですけれど。飯田橋のお堀の近くから、歴史にゆかりのある場所をずっと回ってね。
日置 2009年の「神楽坂伝統芸能」1回目の時ですね。山中室長がガイドで回ってくださっていると聞いて、びっくりした覚えがあります(一同笑)
山中 まあ、みなさんの列が崩れないように、誘導していたぐらいしかできなかったんですけれど(笑) 参加メンバーの1人として、一緒に話を聞かせてもらいました。やはりそれが楽しかったですね。弊社の中には歴史好きも多いので、みんなボランティアを楽しんでやっています。
ーそれが「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」のご協力につながったのですね。
日置 そうですね。「神楽坂伝統芸能」でご協力いただいておりましたから、「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」で、もっと地元のボランティアも集めて大掛かりにやりましょうってなった時に、真っ先にあずさ監査法人さんにご相談に伺いました(笑)
山中 はい、その時もそうでしたね(笑)
ーイベントに参加した際の印象はいかがでしたか?
岩淵 私は一昨年から「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」のボランティアに参加していますが、歴史ガイドの方が場所の説明やいわれを教えてくださって、地域に対する愛情が増しました。また事前のボランティア向け伝統音楽の勉強会でいろいろなことがわかって面白かったです。地元の企業の方と普段会うことは殆どありませんが、イベントをきっかけに知り合って、違う立場だけど同じ目線で協力し合うのも楽しかったです。
ー神楽坂のボランティアに協力してくださってどのように感じられましたか?
山中 私自身、何らかの形で地元にご協力できればと思っておりましたので、とても楽しい時間でしたね。神楽坂の歴史や地域をあらためて知ることが出来ましたし。
他の職員たちも、外国人に説明したり自分の知らないことを尋ねられたりするのが、勉強になっていると。もちろん本人たちもすごく楽しんでくれまして。参加後に社内報でレポートする時に、参加者から感想を聞いたりするのですが、その際に「勉強になった、地域の皆さんと協力できて良かった」との声が毎回出ます。そのような声を聞くと、我々も嬉しくなりますね。
神楽坂は貴重な場所だと思うんですよ。江戸時代からの歴史が残っていて、住んでいる方も芸術家や大学教授、会社員や学生もいるし。ぜひ「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」で神楽坂へ来てもらって、もっと日本の文化芸能を知ってもらう機会が増えればいいなと思います。東京オリンピック・パラリンピックが近いですし、合わせて伝統のある神楽坂のまちの良いところを知ってもらえればと。そして我々も微力ながらお力になれればと思っております。
※1「神楽坂まつり」1972年(昭和47年)に始まったお祭りで、今年で47回目となる。先の2日間がほおずき市、後の2日間は阿波踊り大会。阿波踊り大会では各所より参加した連たちが、来場者にその踊りを披露する。
※2「神楽坂伝統芸能」2009年(平成11年)に始まった、「神楽坂伝統芸能」実行委員会主催のイベント。人間国宝の方が多く住まう神楽坂ならではの上質の伝統芸能を気軽に楽しんで貰いたいと、能楽や長唄、筝や新内や舞踊、そして落語など、様々なイベントを企画し好評を博する。今年は6月に「第10回神楽坂落語まつり」が行われた。



